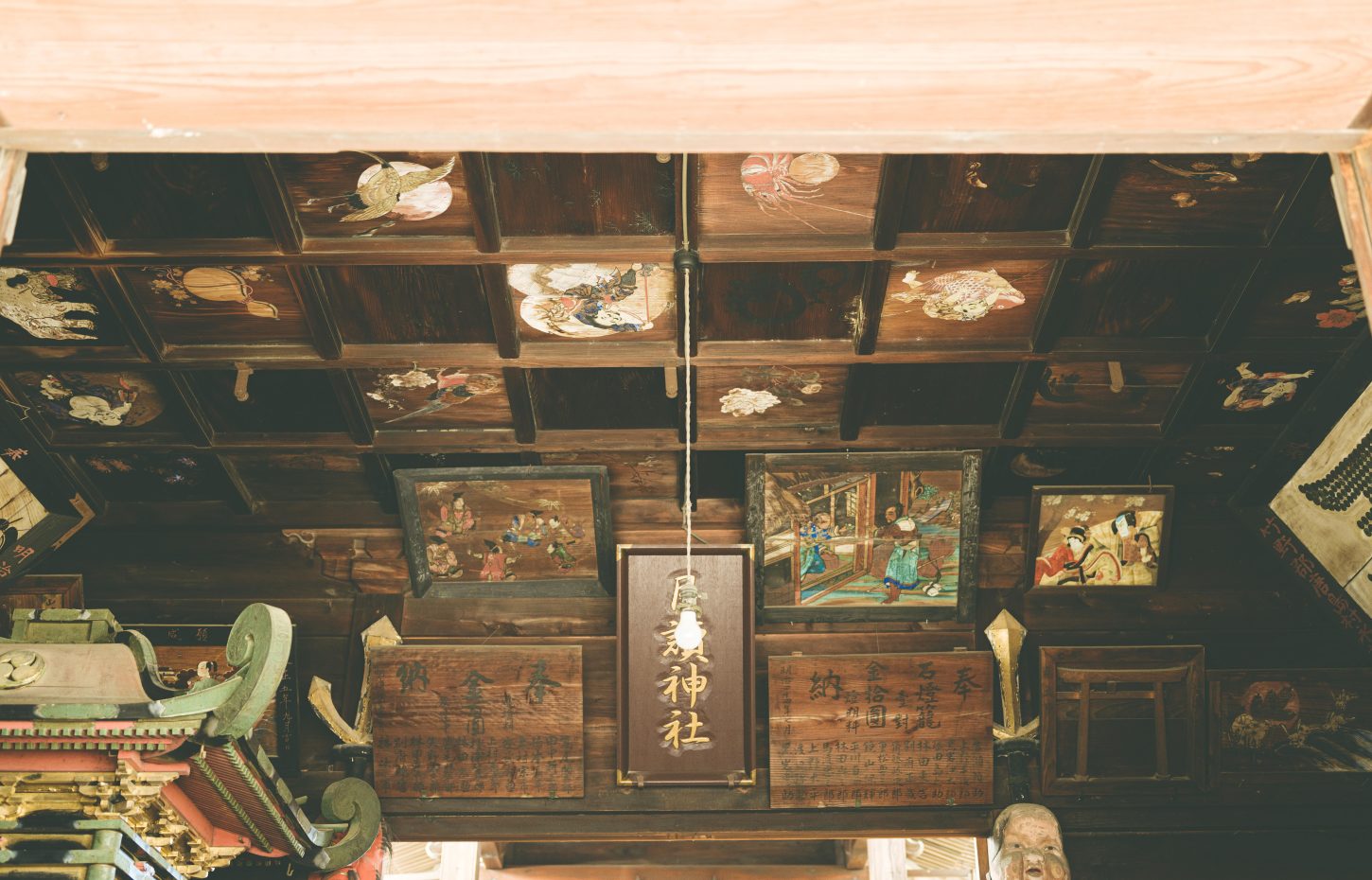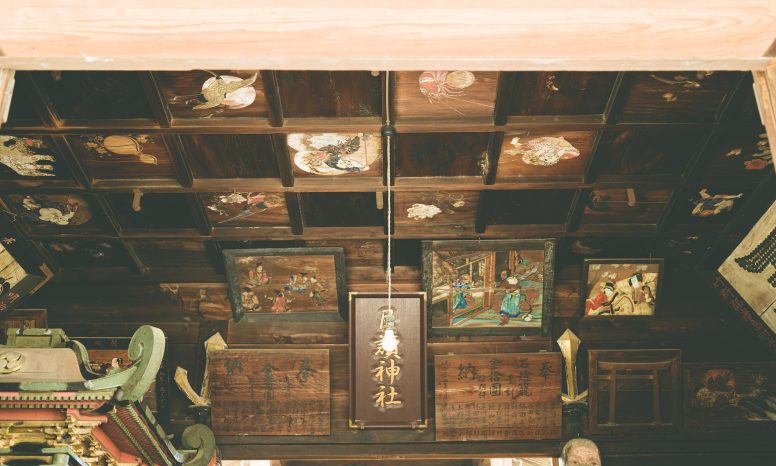変化する神事

狭い範囲に同じ神事が並存する田主丸では、同じ神事でも地区で異なるという面白い発見ができます。ここでは「風止め祭」という神事を例に説明しましょう。
6月末~7月にある風止め祭りは、豪雨や台風による農作物被害、梅雨による疫病の流行がないように祈願します。田主丸中央部に当たる怒田・中舎館・口高地区、また、さらに西の川会地域や筑後川に面した柴刈地域などで行われます。
風止め祭をする神社の中には、境内の木の上に竹柱をくくり付け、その上端に「五穀豊穣・蝗虫駆除」などと記した祈願旗をはためかせます。この作業にクレーンリフトを使う所が多いですが、例えば、怒田地区では今でも人が木登りで行います。旗を立てない場所もありますが、昔はしたのかもしれません。
風止め祭では、地区の境に御幣(ごへい)や厄除け柱を立て、悪霊や疫病が入ってくるのを封じます。御幣も紙垂(しで)を付けたり、御札(おふだ)を竹に挿す、などまちまちです。


厄除け柱も、竹柱の横枝を残すか、御神酒を入れた小筒を付けるか、など隣接する地区同士でも違います。柱の立て方も、道沿いに立てる、人家の敷地内に立てる、標識や電信柱にくくる、と実にさまざま。
風止め祭が別のご神事と合わさった例もあります。西郷・今村・牧地区でも厄除け御幣を立てます。しかし、それは茅の輪(ちのわ)をくぐる「茅の輪くぐり」神事の時なのです。地元の人は風止め祭を知らないと言いますが、実は御札には「風止祭」と書かれています。反対に、柳瀬地区では風止め祭の時に、茅の輪くぐりをします。
茅の輪くぐりも疫病退散・無病息災を祈願する祭りですから、どこかで2つの神事が融合したと思われます。
風止め祭の名だけが残る場合もあります。徳童地区の「風祭」は、久留米市の調査資料では風止め祭と記録されますが、ここでは祈願旗を上げず、御幣も立てないそうです。
このように場所や時代で形を変え、色々な神事が融合していったことが実感できる点も、田主丸の神事の面白さではないでしょうか。